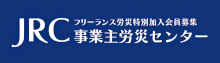お知らせ
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されました。働き方が多様化する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態として労働基準法上 の「労働者」に該当する働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、 労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。これから「業務委託(業務委託の相手方である事業者で、 従業員を使用しないもの)」について一層ご注意が必要になりました。
最近このような裁判例が出てきました^^;
キャバクラで労働契約認定、交通費差し引きは無効 東京地裁が未払い賃金支払い命じる(2025/6/25 19:05)
これまでもさまざまな業種の個人事業主さんから労働者性を主張される事案はございました。しかしこれまでにない業種のみなさん、例えば、配送業、タレントさん、非常勤講師、士業のスタッフ、キャバクラ店キャストさん、様々な業種のみなさんが「業務委託じゃない!私は労働者です!」とご自身の「労働者性」を主張される時代となりました😿
もし業務委託でなく、労働者だと認定されれば、労働基準法が適用されます。普通/深夜/法定休日の割増賃金、週40時間勤務、休日、年次有給休暇、労働保険・社会保険加入、健康診断・・・・数え切れませんが、企業さん側で大きなご負担が生じる可能性大です。ただ、実態がどうなっているのか?対策できることもございます。この機会に企業さん側で、時代の流れと現在の契約の在り方を今一度ご確認いただきたいと思います。
行政のリーフレットはコチラです ↓
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
あなたの働き方をチェックしてみましょう~その働き方、「労働者」ではないですか?~(140KB)
私見ですが、労働基準監督署側でもフリーランスの労働者性について厳しい見方をしている、というのが実感です^^;
企業さまにご注意いただきたいことを一言で申し上げますと、「超短時間の日雇契約かもしれないけど、社員さん同様労働者です!労働基準法が適用されますし、なにも変わりはありません!」です。
※ ここでは、「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこととしています。
※ 「スポットワーク」には様々な形態がありますが、ここでは、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。
行政の詳しい案内はコチラをどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html?c=e20323253b656339-1f34d6086c167505
《2025/07/16》「資格確認書」が従業員ご自宅宛てに郵送されます。
令和7年12月2日以降、現在お持ちの「健康保険証」は使用できなくなります。
(これからもマイナ保険証がなくても大丈夫ですよ~かとうもこの資格確認書を使っていきますよ(^-^))
今後はマイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書が従業員さんご自宅へ送付されます。なお郵送時期は県ごとに異なります。愛知は令和7年7月から、岐阜、三重は10月予定です。
※「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。
行政の詳しい案内はコチラをどうぞ。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
遺族厚生年金の見直しが閣議決定されました!
女性の就業率の向上などに合わせて、遺族厚生年金の男女差を解消することを目的に、男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。
【以下、厚生労働省HP「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」を参考】
-
見直しの対象者
- 法案は2028年4月施行予定です。
- 施行直後に原則5年の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性です。(20代は既に5年の有期給付の対象)。
- 一方、施行直後から妻を亡くした18歳年度末までの子のない男性(20代から50代)は、新たに5年の有期給付を受給できるようになり、年間約1万6千人が対象となる見込みです(女性と同程度に男性も遺族になる場合)。
-
見直しの影響を受けない方
- すでに遺族厚生年金を受給している方、60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響を受けません。
- 18歳年度末までの子がいる方は、子が18歳年度末になるまでの間の給付内容は現行制度と同じです。
-
見直し後の5年の有期給付と継続給付
- 有期給付の額に「有期給付加算」が新たに上乗せされ、5年有期給付の遺族厚生年金は現在の約1.3倍に増額されます。
- 5年有期給付の終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。 具体的には、単身で就労収入が月額約10万円(年間122万円、2025年度税制改正反映で132万円見込み)以下の場合に全額支給され、収入に応じて支給額が調整され、概ね月収20万円から30万円を超えると継続給付は終了します。(※夫と死別した妻で所得要件を満たす「寡婦」の場合、年間204万円程度まで継続給付となる見込みです。)
-
子どもがいるケース
- 18歳年度末までの子がいる方は、子が18歳年度末になるまでは現行制度と同じで、見直しの影響はありません。
- 子が18歳年度末を迎えた後は、さらに5年間は加算によって増額された有期給付の対象となり、その後は上記の継続給付の対象となります。
- また、遺族基礎年金の子の加算額が増額され(年間約23.5万円から約28万円へ)、給付が増えます。
遺族厚生年金における中高齢寡婦加算の見直し
1. 現行制度
- 中高齢寡婦加算の対象者:
- 夫と死別時に40歳以上65歳未満で18歳年度末までの子がない妻。
- 夫と死別時に18歳年度末までの子がいる妻で、遺族基礎年金の支給終了時に40歳以上65歳未満である場合。
- 加算は65歳になるまで支給され、令和7年度の加算額は年額623,800円です。
- 妻を亡くした夫には同様の加算がなく、男女差がある制度となっています。
2. 見直しの背景
- 社会保障審議会年金部会での議論に基づき、女性の就業の進展や共働き世帯の増加を踏まえ、男女間の制度差を解消する目的で、時間をかけて見直しを進めるものです。これは、男女ともに受給しやすい遺族厚生年金を目指す改正の一環です。
3. 見直しの影響を受けない方
- 施行日(令和10年4月1日)前からすでに加算を受け取っている妻は、見直しの影響を受けません。
- 中高齢寡婦加算の対象外である妻(例:40歳未満または65歳以降に夫と死別し、18歳年度末までの子がない妻など)も、見直しの影響はありません。
4. 具体的な見直し内容
- 見直し施行日(令和10年4月1日)以降に新規に発生する加算額は、令和35年度まで25年かけて段階的に縮小されます。
- 一度受け取り始めた加算は、翌年度以降も額は変わらず、65歳になるまで受け取ることができます。
- 今回の遺族厚生年金の見直しで5年間の有期給付となる妻は、有期給付加算により年金額が約1.3倍になった上で、中高齢寡婦加算も受給できます。
- さらに、5年間の支給期間終了後も、障害年金受給権者や収入が十分でない場合は、最長で65歳になるまで、増額された遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算を受給し続けることができます。
- 中高齢寡婦加算の対象者:
いよいよ5月になり気温が高くなってきました。
これから10月ごろまで約半年^^; 熱中症が心配されますね。
毎年増加している熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。
対象となるのは、「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場に
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が必要です😊
熱中症の主な症状は、ふらつき、生あくび、大量の発汗、めまい、筋肉痛、頭痛、吐き気、倦怠感、高体温です。
熱中症は屋内であっても発症します。気温と湿度、両方要注意です!
返事がおかしい?、ぼ~っとしている?、なども要注意です!
「おかしいな?」と思ったら作業から離れ(休ませる)、カラダを冷やし、とにかく医療機関へ!これが基本です。
パンフレット、資料はコチラです。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyam
https://jsite.mhlw.go.jp/toyam
令和7年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和6年度から1/1000(
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率
・一般の事業………
14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000〕
・農林水産業等……
16.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000〕
・建設業……………
17.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000〕
社員さんの4月労働分給与、賞与から控除する雇用保険料を計算する際に用いる率(上記の労働者負担の分の率)も変更しましょう。
育児時短就業給付金
令和7年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
出生時休業支援給付金
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
各支給金の内容と支給申請手続きリーフレット
 育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)[6.7MB]
育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)[6.7MB]
【厚生労働省サイトから引用】
今年の4月、10月と2段階に分けて育児介護休業法の改正があります。
詳しくはコチラへどうぞ。
参考になる規定例(詳細版/簡易版)、そのほか情報提供に使える便利な書式もあります😊
改正事項をまとめたリーフレットはコチラへ。
 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(計6ページ)[461KB]
リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(計6ページ)[461KB]
【厚労省サイトから引用】
【冬季休業】12月28日(土)~1月6日(月)
この間のご用はメール、FAXにてお受けいたします。休業中にいただいたお問い合わせについては、1月7日(火)10:00から順に対応いたします。ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
《2024/12/02》マイナ保険証、マイナンバーについて行政の案内はコチラをどうぞ。
健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて/全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.
マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について/日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/
以前からお伝えしている通り、マイナンバーカード作成は任意です。
マイナンバーカードを作成しただけでは「マイナ保険証」としてご使用になれません。ご自身でマイナポータルへの紐づけ、連携を行ってはじめてマイナンバーカードが「マイナ保険証」として機能します。結論として、マイナンバーカードがなくても黄色カードの「資格確認書」があれば医療機関受診には全く問題ございません。ご安心くださいね😊
労務ご担当者さま、今後の社会保険の資格取得時には「資格確認書要☑」で届出していきましょう。
《2024/10/2》マイナ保険証、マイナンバーについてのお問合せ専用ダイヤルをお伝えします。
どなたでも電話相談ができますので、ご不明な点はお気軽にどうぞ(^-^)
【協会けんぽサイトから引用】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/mndial/?c=e20323253b656339-322910afa0098921
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル
0570-015-369(ナビダイヤル)
8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
※おかけ間違いのないようにご注意ください。
・オンライン資格確認が使えない、正しい資格情報が登録されていない等、マイナ保険証やオンライン資格確認に関するお問い合わせ
・資格情報のお知らせ、資格確認書に関するお問い合わせ
下記22か国語でのお問い合わせに対応しています。
英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・ネパール語・ビルマ語 ・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・マレー語・クメール語・モンゴル語・シンハラ語・ヒンディー語・ベンガル語 ・ウルドゥー語
デジタル庁が開設しているマイナンバーコールセンター
0120-95-0178(フリーダイヤル)
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
(※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日対応)
1.マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
2.マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4.マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
5.マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
6.公金受取口座登録制度及び預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ
《2024/9/2》マイナ保険証についてお伝えします。
・マイナンバーカードをマイナポータル等で健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、黄色のカード「資格確認書」を用いて医療機関等を受診することも可能です。
・令和6年12月2日以降、新規に(転職、就職、扶養追加等)健康保険証は発行されません。みなさんがすでにお持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで従来通り使用できます。
ご参照いただきたい協会けんぽサイトはコチラです。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料(令和6年5月))
↑ 従業員さんへお伝えするときの資料にご活用ください!
毎度おなじみで恐縮ですが・・・
「これからもマイナンバーカード取得は任意です。マイナカードを作らなくても何も起きません!どうかご安心くださいね。」
《2024/8/8》マイナンバーカードによる事故、相変わらずいろいろと報道されていますよね^^;
いつも同じことをお伝えしておりますが、「これからもマイナンバーカード取得は任意です。マイナカードを作らなくても何も起きません!どうかご安心くださいね。」
今日は、今後の保険証の流れをお伝えしますね。
①令和6年9月、令和7年1月に企業宛てに社員さんの個人ごとに封筒で「資格情報のお知らせ」が届きます
「資格情報のお知らせ」には左下に切り取り線がありまして、切り取って個人で保管、もしマイナ保険証を使ったときに機器の不具合等があったときに追加でこれを提示するようです^^;(あら、面倒ですわね)
②令和6年12月2日以降、新規の健康保険証発行は終了します
マイナ保険証をお持ちでないお方に最大5年有効の黄色のカード「資格証明書」が発行されます
2年前ぐらいはマイナ保険証を持っていないお方には申請なしで「資格証明書(ほぼ健康保険証と同じような黄色のカード)」が発行される、と言ってましたが、今年に入って国の様子がおかしいです^^;
2024.6.3かとうが電話でお聞きしました。
「マイナ保険証がない人って今後どうなるの?」
厚労省保険局 医療介護連携政策課へ直電
代表電話03 5253 1111
内線番号3134
大前提:マイナンバーは任意です!
(1)2025.12.1まで現行のプラスチックの保険証は使えます
(2)2024.12.2から現行のプラスチックの保険証は「新規」発行されません
(3)厚労省側がマイナ保険証をすでに使っている人、
使っていない人のデータ集計、それを各保険者(健保等)に送る
(4)2024年10月、各保険者から企業さんへ(3)のデータを送り、
「資格確認書」の必要数を申請してもらう。
マイナ保険証を使っていない人の分は基本的に全員作ってくれる。
その他、「資格確認書」は最長5年使用可能、
データではなく、物理的なもの(黄色のカードのようなもの)だそうです。
今はマイナ保険証を使っていても、今後マイナ保険証を辞めたくなった場合は、
その時点で「資格確認書」の申請が必要になるそうです。
【ご参考】
デジタル庁 よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について
【以下、全国健康保険協会から引用】
↑「資格証明書」は黄色のカードのイメージが掲載されています
【以下、全国保険医団体連合会から引用】
12月以降に資格確認書(=現行の健康保険証)がもらえる人
《2023/5/25》マイナンバーカードによる事故?が相次いでいますね^^;
マイナ健康保険証では、別人登録が7300件、他人さんの医療費や薬の情報を閲覧できたのが5件、他人の銀行口座誤登録が11件、マイナカードを使って住民票を取得したら、他人さんの住民票が出てきた、などなかなか深刻です。結論から申し上げますと、これからもマイナンバーカード取得は任意です。マイナカードを作らなくても何も起きません!どうかご安心くださいね(^_^)
医療機関においてもこれまで通り、通常の健康保険証で受診できます。2023年4月から12月までの期間は、医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料18円の負担となっているようです^^;これをどのように受け止めるか?ですね。
ちなみに現在、わたくしはマイナンバーカードを持っておりません!⇒これで伝わりますよね。そういうことです😁
デジタル庁サイトに分かりやすいQ&Aがありますので、ご案内しますね。
《以下、2023年5月18日現在のデジタル庁サイトから引用》
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について
デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問・疑問について回答します。(2023年5月18日更新)
Q1 オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問合せればよいですか。
A1
万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、以下のいずれかにお問合せいただき、ご相談ください。
- 国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)※音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。
- ご自身が加入されている医療保険の保険者
いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国保中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。
その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの是正作業を速やかに行います。
Q2 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。
A2
マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。ご自身がマイナポータルの対応端末を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険証情報を確認できます。
- ご家族の方等が所持している対応端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
- 市区町村が用意している端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
※端末の設置状況は市区町村によって異なります。
Q3 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。
A3
マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している方なども含め、すべての方々がマイナンバーカードを持ちうるように努めてまいります。なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。
Q4 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。
A4
現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでおり、2023年4月からは、全ての医療機関・薬局において、マイナンバーカード保険証を利用して受診ができるようになります。なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月より改定されています。2023年4月から12月までの期間は、医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料18円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用した方の費用負担が余計にかかるということはなくなりました。
Q5 マイナンバーカードと健康保険証一体化後、マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは保険証が使えないのですか。
A5
紛失等により速やかにマイナンバーカードを再発行する必要がある場合において、現在お受け取りいただくまでに1から2か月かかっている期間を、大幅に短縮してまいります。このような場合に、市町村の窓口で申請をすれば、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るように検討を進めてまいりますので、しばらくお待ちください。それでもなお、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、今後、関係府省と連携しながら、丁寧に対応してまいります。
Q6 マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。
A6
今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、一時利用停止を24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。
Q7 マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。
A7
大丈夫です。マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナンバーだけでは情報を引き出したり、悪用したりすることはできません。 マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本人確認することが義務化されています。 オンラインで利用する時にも、ICチップに入っている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。
Q8 マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。
A8
マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。
Q9 マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。
A9
マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。業務上の必要があって、行政機関間であなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。
《2023/4/12》早くもトラブル発生です!
マイナンバー対応の端末を使っている医療機関で「(端末上でご家族のマイナンバーの確認できないため)あなたのご家族の保険証が使えません!」という状況が発生しています。実際に窓口で10割のお支払いを余儀なくされました。弊所でもびっくりして協会けんぽへ保険証の手続きに間違いがないことを確認(=保険証は完全に有効!)、協会けんぽからは「新たにマイナンバーを登録し直してください」、という回答でした。すでに取得時にマイナンバーを届け出ているからこそ、保険証が発行されているはずです。にもかかわらず、再度マイナンバーを提出???という状態で、弊所としては全く理解できない事象ではございます。その後も数回にわたり、弊所から管轄の年金事務所、協会けんぽに確認、各行政から本省へ確認してくれまして、なんと本日段階で判明したことは以下のとおりです。(長くなり申し訳ございません^^;)
●令和3年2月1日以前に届け出たご家族のマイナンバーは、(日本年金機構から)協会けんぽに伝わっていない。=小職はソフト上の問題と捉えています。
●令和3年2月1日以前に届け出たご家族の健康保険証に、協会けんぽのデータ上ご家族のマイナンバーが紐づけされていない状態になっている。
●協会けんぽのデータ上ご家族のマイナンバーの紐づけがされていない状態なので、医療機関窓口で「ご家族のマイナンバーの確認できないため、あなたのご家族の保険証は使えません!」、10割請求される。
《みなさまへお伝えしたいことは3つです》
●協会けんぽから企業さまへ「ご家族のマイナンバーを記載して返送してください」というお手紙が発送されているそうです。お手数ですが、ご記入とご返送にご協力ください。
●お急ぎの場合、弊所から協会けんぽへお困りのご家族のマイナンバーを再度申請します。協会けんぽ内でマイナンバー登録に約2週間はかかる、それ以降なら医療機関窓口で保険証が利用可能、となるそうです。
●どうしても7割分を医療機関窓口精算できないときは、お手数とお時間を頂戴しますが「療養費」でけんぽ協会へ請求します。
《2023/3/16》もともと令和3年10月から本格運用されているはずのマイナンバーカードの健康保険証利用、わたくしはお試しに?利用登録は済ませておりますが、一度も利用したことがありません^^;笑っちゃう話しですが、わたくしが通う歯科クリニックには受付のところに「(みなさんが毎日)マイナンバーカードを持ち歩いたら個人情報がアブナイから、保険証は今のままがいいですよ!」みたいな大きなポスターがありました😁面白くて印象に残っています。今日現在は、このポスターはありませんでした(なんで???)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
厚労省は大丈夫!って言ってますが、これはどうでしょうかね^^;
マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた
上記動画で平井大臣は「マイナカードのICチップはキーホルダーのようなモノ」と言っていました。(???)
フツーに「失くしちゃダメ!表面だけを見せてね。」って書いてあるだけです。
皆さん、よくよくご存知のことです。
「マイナンバーカードの健康保険証利用」詳しい厚生労働省特設サイトはコチラです。
マイナンバーカードの取得はあくまで任意ですので、これからいろいろお調べいただいてご判断、で良いと思います。
確かにマイナンバーカードで保険証利用ができれば便利なこともあります。
会社で資格取得届が提出されていれば、実際の保険証の発行を待たなくても医療機関で使用可能、別に発行されている高齢受給者証、高額療養時に限度額認定証なども提示不要、マイナポータルから医療費費用のデータを取得可能、など、便利になるようです。
しかしながら、オンライン資格管理を導入しない医療機関では、従来どおり健康保険証を提示して受診します。そして今後も従来の健康保険証で医療機関を受診できます。
みなさま、どうかご安心くださいね(^_^)
カードリーダー備え付けの申請が9割超えている、との報道もありますが、もう3月ですが、まだ「申請」???
備え付けて初めて利用できるわけですから、わたくしたちに考える時間は十分にありますね。
運転免許証や銀行口座も紐付けられる日が来ちゃうんでしょうかね(T_T)